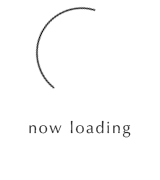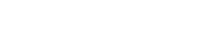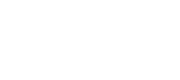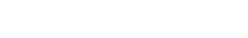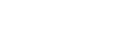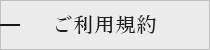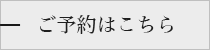体重増減物語
2023.11.30
ウイーンで暮らした1年半で、僕の体重は10キロ減った。
「日本のご飯でないと受け付けない」と、強く感じていたわけではない。
また、ダイエットしなくちゃとも思っていたわけではない。
当時を振り返ると、少しずつダメージが蓄積した結果なのかもしれないと思うようになっていた。
どうも要因はこのあたりにありそうだ。
①水が違う
②食材が違う
③大皿料理を作らなくなる
④物価が高い
⑤結果として食事量が減る
⑥よく歩く
①水が違う
移住時の荷物に、日本のスーパーマーケットで売られているカレールーを持参した。日本では常用していたものだが、それを使ってカレーライスを作るのだが味が全く違う。おいしくないのだ。
お茶、出汁なども、やはり味がずれている。
「味覚は大雑把」を自認しているのだが、どれもおいしいと思えない。
②食材が違う
野菜・肉・魚、多くは日本で売られているものとは少しずつ違う。
一番閉口したのはキャベツ。どれだけ煮ても焼いても、筋っぽさが抜けない。お好み焼きではおなじみの食材だが、何回目かには白菜に切り替えた。
もちろん安くて同じような味・触感のものはある。カリフラワー、インゲン類は多用した。
肉は薄切りはなく、ほとんどが赤み肉でそれがほぼ塊で売られている。メニューが思いつきにくいのと、どの肉も多少動物臭がある。
オーストリアは海がない内陸国なので、普通のスーパーに鮮魚はほぼない。大型スーパーや市場にはあるのだが、鮮魚はかなり高いし、それを生かす腕がない。
③大皿料理を作らなくなる
そんな中で日々自炊をしていると、メインの肉あるいは魚に付け合わせのワンプレートという洋風メニューが定着してきた。つまり、一人分の食事を夫婦分2皿だけ作るということになってきたのだ。
日本にいた頃は娘がいたので、数種類のおかずを大皿でというスタイル。したがって、個人の分量は「満腹になったらおしまい」という判断にゆだねられていた。
④物価が高い
オーストリアの人口は、大阪府民とほぼ同数。とても小さな国だが、一人当たりGDPは、日本よりはるか上にあり、ヨーロッパの中でもかなり豊かな国に位置する。ここで住んでいると、日本の収入も物価も安いことが、日本の活力を奪っているのがよくわかる。
そんな中でウイーンのスーパーマーケットの価格もレストランも、そんな日本人の感覚すると高い。今の異常なほどの円安を勘案すると、物価全般に、日本の2倍といっても過言ではないのではないか。それほどオーストリアの収入は日本に比べて高いのだ。
⑤結果として食事量が減る
結果としてウイーンでの食事の分量は、減少傾向にあったのだと思う。つまり年齢にふさわしい量になっていたのだと思う。
⑥よく歩く
ヨーロッパの車の標準は、左ハンドル、右側通行。日本の事情の真逆。だから、最初から自家用車を購入することは想定していなかった。
ウイーン市内は、地下鉄・トラム・バスがとてもよく整備されている。最も安い30日パスを購入すると、1日0.6ユーロ(約100円)で乗り放題になる。日々の暮らしはこれで十分。
ドアからドアまで車で移動する田舎よりも、公共交通機関中心の都会の暮らしは歩数が断然多くなる。私たちには通勤・買い物などが、適切な運動になったのだろう。
日本に戻って、半年で体重は移住前に戻った。原因は単純で、食事も運動も移住前に戻ったということだ。60歳を前にしてウイーンで暮らし始めたのだが、長年蓄積された味覚が1年半では覆せなかったということなのだろう。
オーストリアへの移住には、ポイント制の申請資格が必要だった。語学力や職能・職歴などでポイントが加算されるのだが、年齢もその対象だった。若ければ若いほどそのポイントは高い。申請時の私の年齢加算はゼロだった。
その判断は、ある意味正解なのかもしれない。